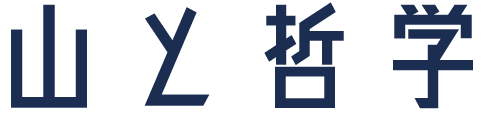ポップなリバプールサウンドに対抗して、夜の街ロンドンでブルースやR&Bを基調としたブリティッシュロックが産声をあげる、というような文脈です。よろしければ、リバプールサウンドの話に先に目を通していただくとよいかと。
 60年代に世界を席巻したリバプールサウンドっていったい何だったのか?
60年代に世界を席巻したリバプールサウンドっていったい何だったのか?
とくに続き物というわけではありませんので、このまま⬇へ行ってもらってももちろん大丈夫です。
もくじ
イギリス風ブルース、R&Bはロンドンのナイトクラブで誕生
ビートルズを筆頭とするリバプールサウンドがロンドン中心に盛りあがっていたころ、地元ロンドンの遊び人たちはブルースやR&Bにひそかに熱くなっていた。
彼らはポップなリバプール系を嫌い、ブラックミュージックに傾倒していた。そこから次第にロンドン独自のブルースやR&Bをベースにした音楽が生まれてくる。
最初はブルースやR&Bのコピーバンドとしてスタートしたが、やがてオリジナル曲もできる。メジャーデビューにこぎつけるバンドも出てくる。そうなるとヒットチャートを意識せざるをえない状況を経験する。そうしたなか、商業主義音楽への反発心がスピリットとなり、のちのブリティッシュロックへと発展していった。
ブリティッシュロックが世に出て、注目を集める
その代表格はもちろん、ローリング・ストーンズだが、ほかにもさまざまなバンドが世に出てきた。
アニマルズ
たとえばニューキャッスル出身のアニマルズは、「朝日のあたる家」のビッグヒットで世界に名を轟かせた。人気絶頂期に来日し、熱のこもった演奏で日本のミュージシャンらに強いインパクトを残している。
マンフレッドマン
アニマルズほどではないが、マンフレッドマンも「ドゥーワ・ディ・ディ・ディ」や「シャララ」などのヒット曲を持ち、実力派として人気を獲得していた。
ダークでフォーマルなファッションで、アダルトな雰囲気を演出。息の長いグループで、1960年代後半も時代に合わせて音楽をつくりつづけていたが、イマイチ焦点が定まらず、固定ファンをつかむまでにはいたらなかった。
その後もチャプター3、アースバンドと変化をつづけていく。
キンクス
マンフレッドマンにくらべると、デビュー当時から少数だが熱狂的なファンをつかんでいたのはキンクスだ。熱烈なビートと気だるい歌は、イギリスならではのロックサウンドといえるものだった。
彼らを知らなくても、日本でのデビューシングル「ユー・リアリー・ガット・ミー」くらいは聴いたことがあるはず。
ヤードバーズ
解散してから人気が出たバンドもある。ヤードバーズだ。
エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジという3大ギタリストを輩出したことで知られるが、じつはシングル盤ではかなりポピュラーな曲も出している。それらはそれなりのヒットを飛ばしてもいる。
「フォー・ユア・ラブ」はクラプトンが脱退するきっかけとなった曲。
1966年、第2期ブリティッシュサウンドの雄が続々登場
1966年ごろには、第2期ブリティッシュサウンドとでも呼べる新しいグループが次々と登場する。ザ・フー、スモール・フェイセス、スペンサー・デイヴィス・グループらだ。
彼らもそれ以前から活動していたのだが、この時期になって、それぞれ新しい音で人気をつかんでいった。
ザ・フーやスモール・フェイセスはまず見た目が注目を集めた。これまでにない服装、いわゆる「モッズ・ファッション」だ。むろん身なりだけでなく、ときに破壊的、ときに硬派な音楽性にも注目が集まった。
ザ・フー
1965年リリースの3枚目のシングル「マイ・ジェネレーション」はイギリスのチャートで2位という快挙。彼らの名を一気にスターダムにのしあげた。
スモール・フェイセス
1966年に全英1位獲得の「オール・オア・ナッシング」。ボーカルのシャウトとギターリフが相当イケてる。いかにもなモッズ・ファッションもかなりイケてる。
スペンサー・デイヴィス・グループ
スペンサー・デイヴィス・グループは当時まだ10代だったスティーブ・ウィンウッドがボーカルを担当。期待の新人として、日本のロックミュージシャンのあいだでも話題を呼んだ。
1967年の「愛しておくれ」は彼らの代表曲。サントリーの発泡酒のCMソングに使われていたのが記憶に新しい。アメリカのビルボード・チャートでも7位まで上昇した。
ブリティッシュロック界のドン、ローリング・ストーンズ
海の向こうではブリティッシュサウンドが新風を巻き起こしていたのだけれど、前述のような実力派でさえも日本でレコードが発売されることはあまりなかった。ストーンズはおろかビートルズにしても、イギリスのグループのヒット曲は、ほとんどがアメリカ経由で輸入されていたからだ。
ようやくビートルズがアメリカ進出を果たし、それまでイギリス国内で活躍していたバンドの多くが、その系譜や評価もはっきりしないまま十把ひとからげに日本で紹介されていたのだ。
こうしたなか、アメリカで大したヒットソングのないストーンズには、どういうわけだか大物の貫禄があった。
「リバプールのビートルズに対抗するロンドンからの答え、それがストーンズ』(初期の宣伝コピー)
こんな「VSビートルズ」作戦が功を奏したのか、雑誌などを中心に「ビートルズのライバル」というイメージが定着していたからである。
だが実際のところ、レコードのセールスではビートルズの足元にもおよばなかった。1966年時点の集計で、ビートルズのセールスが1億5000万枚なのに対し、ストーンズは1000万枚程度。ビートルズのシングル「抱きしめたい」と同じだ。しかしこの成績であれだけエラそうにふるまえるのだから、やはり大物であることはまちがいない。
「サティスファクション」の大ヒットで、真にビートルズのライバルへ昇格
そうした状況も、1965年の「サティスファクション」のメガヒットで一転する。過去にリリースしたもののあまり売れていないレコードにも注目が集まるようになり、さらに1966年以降は音楽性の面でもめきめきステップアップ。名実ともにビートルズのライバルとして、その名をほしいままにしていく。
ストーンズがビートルズの好敵手という評価は妥当なのだろうか
 ヒマワリ
ヒマワリ
尾崎と浜省は同じくらい好きです。ミックとジョンだと完全にジョンです。だからジョンに肩入れしていると思われるかもしれませんが、いや実際そうなのかもしれませんが、ストーンズがビートルズのライバルだという話を聞くと背中がムズムズします。
ミックに劣等感はあったかもしれない。けどビートルズ、とくにジョンはミックのことをライバルだなんて毛ほども思ってなかったと思うのです。『ローリング・ストーン』誌の1971年1、2月号に掲載されたジョンのインタビューを初めて読んだときもそう感じました。
——いまのストーンズについては、どう思いますか。
たいへんなごまかしだと思います。私は「ホンキー・トンク・ウーマン」が好きで、ミックは一種のジョークだと思うのです。私がいつもやっていたオカマの踊りを、いま彼はさかんにやっています。私は彼を楽しんで見ています。彼が出ている映画とかそういったものは、ほかの人たちとおなじく、みんな見にいくでしょうけれど、ほんとうに、彼はジョークなのです。
——いまでも彼によく会いますか。
いいえ、まず会いません。アレン(・クライン。ビートルズ後期のマネージャー)が入ってきつつあったころには、おたがいにすこしは会ったのですけれど。ミックは私に嫉妬しているのだと思います。しかし、私は、ミックやストーンズに対しては、いつも敬意を表していました。にもかかわらず、ミックは、ビートルズについて、けなすようなことをたくさん言いました。私はそれで傷つけられているのです。なぜなら、私はビートルズをやっつけることができますけれど、ミック・ジャガーにやっつけられることはないと思うからです。私たちがやってきたことをまずリストにこしらえ、ふた月おくれでストーンズがおこなったことを、どのアルバム、どんなことについてでもつきあわせて調べていけば、ミックは、ビートルズとまったく同じことをおこなっている事実がわかるはずです——彼は私たちを真似しているのです。あなたのようなアンダーグラウンドの人に、そのことを活字にしてもらいたいですね。『サタニック・マジェスティ』が『サージェント・ペパー』だということは、よく分かるはずです。「ウイ・ラヴ・ユー」は、これこそもっともくだらないですね、「オール・ユー・ニード・イズ・ラヴ 」なのですから。
ストーンズは革命的でビートルズはそうではなかった、というような言い方に、私は憤慨します。もしストーンズが革命的であったり、いまでも革命的であるというなら、ビートルズもほんとうに革命分子だったのです。ビートルズとストーンズでは、音楽的にも影響力の面でも、クラスがちがいます。おなじクラスだったことは一度もありません。私は、ストーンズのことを悪く言ったことは一度だってないのです。ストーンズは、いつも敬愛していました。彼らのファンキーな音楽やスタイルが好きだからです。ロックンロールは好きだし、ビートルズの真似をやめてからストーンズがとった方向も、好きです。
自分たちとくらべて、ビートルズはあまりにも大きすぎるので、ミックはそのことが気になってしかたがないんです。いまだに気にしていますね。彼もいまではそれなりに歳をとってきて、ビートルズにあれこれ難癖をつけるようになってきていますよ。これからも悪口を言いつづけますよ。私にとっては腹の立つことですね。彼らの二枚目のレコードにしたって、ビートルズが曲をつくったようなものですから。「平和はおかねになった」とミックは言ってますけれど、僕たちは平和で金儲けはしてません。
インタビュアー/ヤーン・ウェーナー
出典/『ローリング・ストーン』誌(1971年1、2月号)から
 ヒマワリ
ヒマワリ
日本でもストーンズ再認識の大波がやってきた
世界でのストーンズの評価が高まるなか、日本でも独自にストーンズ再認識の動きが起きる。立役者は、1968年ごろから大ブームを巻き起こしていたグループサウンズだ。
彼らのなかに熱心なストーンズファンがたくさんいた。ザ・タイガースはステージでかならずストーンズナンバーを演奏、ザ・テンプターズはミック・ジャガーをもろに意識していた。
日本のGSやミュージシャンにはストーンズファンが多かった
タイガースやテンプターズのストーンズ好きはことのほか有名だった。ジュリー(沢田研二)はソロになってからもストーンズの曲をやっていたし、ショーケン(萩原健一)は「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」が十八番。
ほかにも多くのグループサウンズや、忌野清志郎や鮎川誠、Charなど、ストーンズに影響を受けたというミュージシャンは数しれない。
 ヒマワリ
ヒマワリ
こうしたグループサウンズの演奏によって、「テル・ミー」や「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」などを初めて聴いた若いファンたちがストーンズに注目しはじめる。
シングル盤が再発され、チャートを駆けのぼる。LPもジャケットを変えてリニューアル発売される。こうしてストーンズの人気は国内でも着実に高まっていったのだ。
「テル・ミー」(1964年)
ミックとキースの共作としては初となる曲。1964年にシングルカットされ、アメリカで初のトップ40入り。日本でも発売され、この曲をきっかけにストーンズの名が浸透しはじめた。
「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」(1964年)
アメリカのジャズミュージシャン、カイ・ウィンディングが1963年にリリースした楽曲をカバーし、シングルとして発売。ビルボードチャートの6位を記録した。
レコードデビューは1963年。それから27年の時を経て、ようやく待望の来日も果たす。
ストーンズはいまなおブリティッシュロックのスピリットを保ち、僕らにそれを聴かせつづけてくれている。